牛肉は良質なタンパク質を含む食材として、多くの人に親しまれています。
しかし、牛肉の部位ごとのタンパク質含有量は異なり、目的に応じて適切な部位を選ぶことが重要です。
たとえば、筋トレやダイエットを意識するなら、高タンパクで低脂質な部位を選ぶのが効果的です。
また、牛肉だけでなく、豚肉や鶏肉もタンパク質を豊富に含んでいます。
では、牛肉と豚肉と鶏肉のタンパク質量を比較した場合、それぞれどのような違いがあるのでしょうか。
さらに、肉類以外にも、効率よくタンパク質を摂取できる食品があります。
食事のバランスを考えるなら、タンパク質の多い食品も知っておくことが大切です。
この記事では、牛肉100gあたりのタンパク質量を中心に、部位ごとの特徴や他の肉類との比較、さらに高タンパクな食材について詳しく解説します。
目的に合ったタンパク質の摂取方法を知り、効率的に栄養を取り入れましょう。
この記事を読むことで理解できる内容は以下の通りです
- 牛肉の部位ごとのタンパク質含有量の違いを理解できる
- 牛肉と豚肉、鶏肉のタンパク質量を比較できる
- タンパク質の多い食品とその特徴を知ることができる
- 牛肉のタンパク質を効果的に摂取する方法を学べる
牛肉 100g タンパク質はどのくらい?他の肉と比較
- 牛肉の部位ごとのタンパク質含有量一覧
- 牛肉と豚肉のタンパク質量を比較
- 牛肉と鶏肉のタンパク質量を比較
- タンパク質の多い食品ランキング
- 牛肉のタンパク質を効果的に摂取する方法
牛肉の部位ごとのタンパク質含有量一覧

牛肉は部位によってタンパク質の含有量が異なります。
同じ牛肉でも、脂肪の量や筋肉の発達度合いによってタンパク質の割合が変わるため、栄養面を意識して部位を選ぶことが重要です。
ここでは、日本食品標準成分表2020年版(八訂)をもとに、主要な部位の100gあたりのタンパク質量をまとめました。
まず、高タンパク低脂質の代表格として「ヒレ肉」が挙げられます。
ヒレ肉は21.9gのタンパク質を含み、脂質が少なく、柔らかい食感が特徴です。
次いで「もも肉(赤身)」は20.3g、「もも肉(脂身なし)」は21.9gと、こちらも高タンパクで脂質が控えめな部位です。
筋トレやダイエットを意識する方にとっては、これらの部位が最適でしょう。
一方、「バラ肉」や「リブロース肉」は脂質が多くなる傾向があります。
バラ肉の赤身部分は18.1g、脂身を取り除いた場合は20.5gのタンパク質を含みます。
リブロース肉も赤身の状態では19.8g、脂身を除いた場合は21.1gと、脂肪の量によって変動します。
また、「ウデ肉」は赤身で20.0g、脂身を除くと21.3gのタンパク質を含んでおり、比較的安価で手に入るため日常的に活用しやすい部位です。
「タン(舌)」は16.4g、「レバー(肝臓)」は19.5gと、内臓系もタンパク質を含んでいますが、レバーは鉄分も豊富で栄養価が高いという特徴があります。
このように、牛肉の部位ごとにタンパク質含有量が異なるため、目的に応じて部位を選ぶことで、効率的に栄養を摂取できます。
脂質を抑えたい場合はヒレ肉やもも肉を選び、風味や食感を重視する場合はリブロースやバラ肉を活用するなど、用途に応じて選択するとよいでしょう。
牛肉と豚肉のタンパク質量を比較

牛肉と豚肉のタンパク質量は、おおよそ同じくらいに思われがちですが、実際には部位ごとに違いがあります。
どちらの肉がより高タンパクなのか、またそれぞれの特徴について詳しく見ていきましょう。
まず、牛肉の高タンパク部位としてヒレ肉があり、100gあたり21.9gのタンパク質を含んでいます。
一方、豚肉のヒレ肉も同じく21.9gと、ほぼ同じ水準です。
次に、もも肉のタンパク質量を比較すると、牛肉のもも肉(赤身)が20.3g、豚肉のもも肉(赤身)は20.0gとなり、こちらも大きな差はありません。
しかし、脂質を含む部位では若干の違いが見られます。
例えば、ロース肉の場合、牛肉(赤身)は20.7g、豚肉(赤身)は21.7gと、豚肉の方が若干多くなっています。
また、バラ肉(赤身)では、牛肉が18.1g、豚肉が19.1gと、豚肉の方がやや多くタンパク質を含んでいます。
また、内臓系では牛レバーが19.5g、豚レバーが19.6gと、ほぼ同等の数値です。
ただし、鉄分やビタミンの含有量は豚レバーの方が多いことが知られています。
このように、牛肉と豚肉のタンパク質量はほぼ同程度であることがわかります。
しかし、脂質やミネラルのバランスが異なるため、食べる目的によって選択するのがよいでしょう。
筋肉を増やしたい場合は、どちらの肉もヒレ肉やもも肉を選ぶと良いですし、脂質を活かした料理をしたい場合は豚のバラ肉や牛のリブロースを活用するのが適しています。
牛肉と鶏肉のタンパク質量を比較

牛肉と鶏肉を比較すると、タンパク質量の面では鶏肉がやや優勢です。
特に「鶏むね肉(皮なし)」は23.3gのタンパク質を含み、牛肉のどの部位よりも多くなっています。
牛肉のヒレ肉は21.9g、もも肉(赤身)は20.3gと高タンパクな部位ですが、それでも鶏むね肉には及びません。
また、鶏のささみは23.1gと、こちらも牛肉を上回る数値です。
ただし、鶏肉は部位によってタンパク質量にばらつきがあります。
例えば、「もも肉(皮つき)」は18.6g、「手羽元(皮つき)」は16.4gと、牛肉のもも肉やウデ肉と同じくらいの数値になります。
一方で、牛肉には鉄分や亜鉛が豊富に含まれており、特に貧血予防には適しています。
さらに、牛肉は旨味が強く、調理のバリエーションが豊富であるため、食事の満足度が高いというメリットがあります。
そのため、タンパク質の摂取を最優先するなら鶏むね肉が最適ですが、栄養バランスや味わいを重視する場合は牛肉も積極的に取り入れるとよいでしょう。
タンパク質の多い食品ランキング
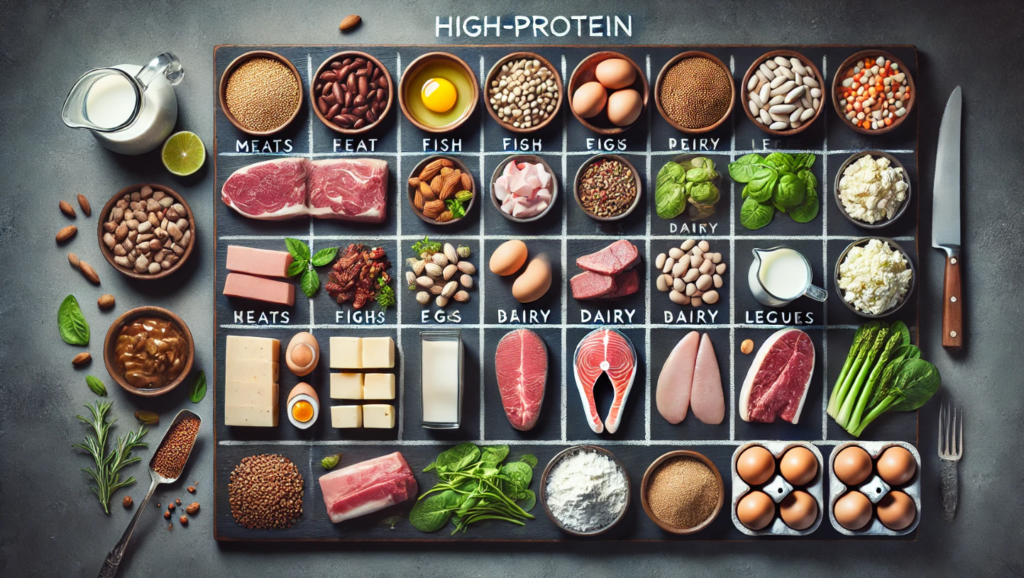
タンパク質を効率よく摂取するためには、肉類だけでなく、魚介類や大豆製品などの食品も活用することが大切です。
以下、代表的な食品のタンパク質含有量(100gあたり)をランキング形式で紹介します。
- 鶏むね肉(皮なし):23.3g
- 鶏ささみ:23.1g
- 牛ヒレ肉:21.9g
- 豚ヒレ肉:21.9g
- マグロ赤身:21.7g
- 納豆:16.5g
- 卵(全卵):12.3g
肉類では鶏肉が圧倒的に高タンパクですが、魚介類も豊富なタンパク質を含みます。
また、納豆や卵は植物性・動物性の両方のタンパク質をバランスよく摂取できる食品としておすすめです。
牛肉のタンパク質を効果的に摂取する方法

牛肉のタンパク質を効率よく摂取するためには、部位の選び方や調理法が重要です。
まず、タンパク質を多く含む部位としては、ヒレ肉やもも肉が最適です。
脂質を抑えながらタンパク質を摂取できるため、健康を意識する方におすすめです。
調理法としては、煮込みや蒸し調理を活用すると、余分な脂を落としつつ栄養を逃がさずに摂取できます。
また、レモンやビタミンCを含む食材と一緒に摂ることで、鉄分の吸収率が向上するため、栄養面でも効果的です。
こうした工夫を取り入れることで、牛肉の持つタンパク質や栄養素を最大限に活用できるでしょう。
牛肉 100g タンパク質の効果と適切な摂取量
- タンパク質の効果と健康への影響
- 1日に必要なタンパク質の摂取量とは
- タンパク質摂り過ぎのリスクと注意点
- 牛肉を効率的に摂取するおすすめ調理法
- 牛肉以外のタンパク質源もバランスよく摂るべき理由
タンパク質の効果と健康への影響

タンパク質は、私たちの体にとって欠かせない栄養素の一つです。
筋肉や皮膚、髪の毛、爪、内臓、ホルモン、酵素など、あらゆる組織の構成要素として機能しており、健康維持に大きく関わっています。
特に、筋肉の維持や成長には欠かせない栄養素であり、運動をする人だけでなく、加齢による筋力低下を防ぎたい人にとっても重要です。
タンパク質の効果として、まず「筋肉の維持と成長」が挙げられます。
運動後にタンパク質を摂取することで、筋肉の修復が促進され、筋肉量を増やす手助けとなります。
また、基礎代謝が上がるため、ダイエット中の方にも有益です。
タンパク質は消化・吸収に時間がかかるため、食後の満腹感が持続しやすく、間食の防止にも役立ちます。
さらに、免疫力の向上にも寄与します。
体内の免疫細胞の多くはタンパク質によって構成されているため、十分な量を摂取することで、風邪や感染症に対する抵抗力を高めることが期待できます。
また、肌や髪の健康を保つ働きもあり、コラーゲンの生成を促すことで、シワやたるみの予防にもつながります。
一方で、タンパク質の摂取量が不足すると、筋肉量の減少、免疫機能の低下、肌や髪のダメージなど、さまざまな健康リスクが生じます。
特に高齢者の場合、タンパク質不足が原因でサルコペニア(筋肉減少症)を引き起こし、日常生活に支障をきたす可能性もあります。
このように、タンパク質は体の健康を支える重要な栄養素であり、適切な量を日常的に摂取することが必要です。
ただし、過剰に摂取しすぎると、腎臓に負担がかかる可能性があるため、バランスを意識しながら食事に取り入れることが大切です。
1日に必要なタンパク質の摂取量とは
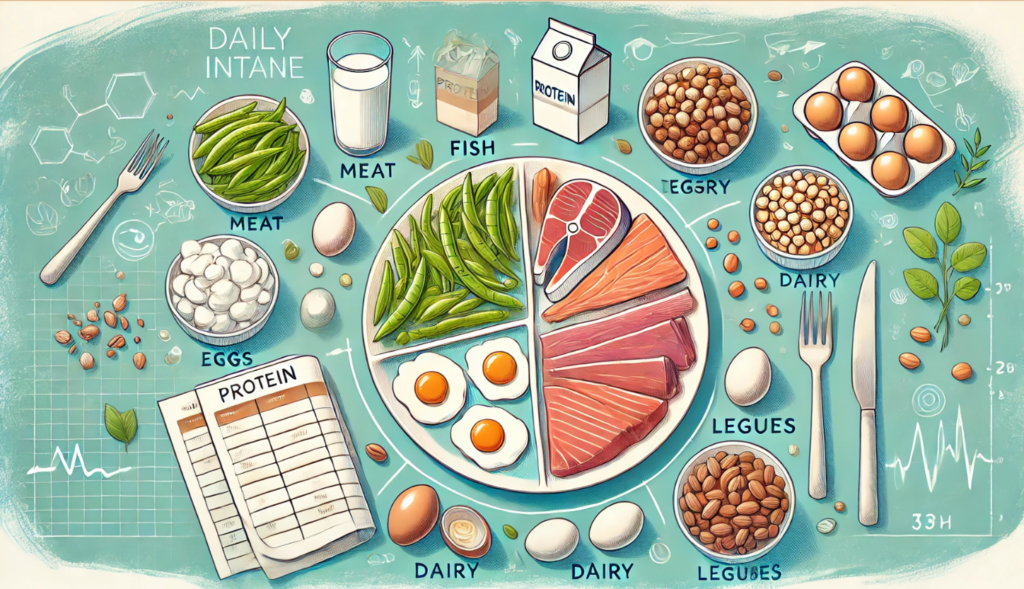
私たちの体が正常に機能するためには、適量のタンパク質を毎日摂取する必要があります。
厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」によると、成人男性の推奨タンパク質摂取量は1日65g、成人女性は50gとされています。
しかし、この数値はあくまで最低限の目安であり、生活習慣や身体活動レベルによって必要量は変わってきます。
例えば、運動習慣のある人や筋肉量を増やしたい人の場合、体重1kgあたり1.2〜2.0g程度のタンパク質を摂ることが推奨されています。
体重60kgの人であれば、1日に72〜120gのタンパク質が必要になる計算です。
また、高齢者の場合、筋力低下を防ぐために一般的な成人よりもやや多めに摂取することが勧められています。
タンパク質は1回の食事でまとめて摂るよりも、3食に分けて摂取する方が効果的です。
体内でのタンパク質合成は一定の速度で行われるため、一度に大量に摂取してもすべてが活用されるわけではありません。
そのため、朝・昼・夜のバランスを考えて、毎食にタンパク質源を取り入れることが重要です。
また、食材ごとに含まれるタンパク質量を把握し、食事に取り入れる工夫も必要です。
例えば、牛肉100gには約20gのタンパク質が含まれていますが、卵1個では約6g、納豆1パックでは約8gとなります。
これらを組み合わせることで、バランスよく必要量を摂取することができます。
タンパク質摂り過ぎのリスクと注意点

タンパク質は健康に欠かせない栄養素ですが、過剰に摂取すると体に負担がかかる可能性があります。
特に腎臓や肝臓に疾患がある場合は、注意が必要です。
過剰摂取のリスクとして最も懸念されるのが「腎臓への負担」です。
タンパク質の代謝によって生じる老廃物(尿素やアンモニア)は腎臓を通じて排出されますが、過剰に摂取すると腎臓の負担が増し、腎機能の低下を招く可能性があります。
特に、慢性腎臓病のリスクがある人は、医師の指導のもと適切な量を守ることが大切です。
また、腸内環境への影響も見逃せません。
タンパク質の摂りすぎは腸内の悪玉菌を増やし、便秘や腸内ガスの増加につながることがあります。
特に、肉類中心の食生活で野菜や食物繊維が不足すると、消化不良を起こしやすくなります。
このようなリスクを避けるためには、タンパク質摂取のバランスを考え、肉類・魚・大豆製品など、さまざまな食品から摂取することが重要です。
また、水分を十分に摂り、腎臓の負担を軽減することも忘れてはいけません。
牛肉を効率的に摂取するおすすめ調理法

牛肉のタンパク質を効率よく摂取するためには、調理法にも工夫が必要です。
例えば、焼く・茹でる・蒸すなどの方法を使い、余分な脂肪を落としながらタンパク質をしっかり摂るのが理想的です。
最もシンプルで手軽な方法は「グリル」です。
脂質の多い部位でも、焼くことで余分な脂が落ち、ヘルシーに仕上がります。
また、「茹でる」調理法もおすすめで、しゃぶしゃぶのように脂を湯に落とすことで、脂質を抑えつつタンパク質を効率よく摂ることができます。
さらに、消化吸収を良くするために「細かく刻む」「ミンチ状にする」といった工夫も有効です。
例えば、牛ひき肉を使ったハンバーグやそぼろは、胃腸への負担が少なく、子どもや高齢者でも食べやすくなります。
牛肉以外のタンパク質源もバランスよく摂るべき理由

牛肉は優れたタンパク質源ですが、それだけに偏ると栄養が偏りがちです。
そのため、他のタンパク質源もバランスよく取り入れることが重要です。
例えば、魚にはDHAやEPAといった良質な脂肪酸が含まれ、鶏肉は低脂質で高タンパクです。
さらに、大豆製品は食物繊維が豊富で、腸内環境を整える効果もあります。
このように、複数の食品を組み合わせることで、タンパク質だけでなく、ビタミンやミネラルもバランスよく摂取することができます。
牛肉100gのタンパク質と他の肉を比較!高タンパク食材ランキング:まとめ
この記事のまとめです。
- 牛肉のタンパク質量は部位によって異なる
- ヒレ肉やもも肉は高タンパク・低脂質である
- バラ肉やリブロースは脂質が多めの部位である
- 牛肉と豚肉のタンパク質量はほぼ同じ
- 牛ヒレ肉と豚ヒレ肉はどちらも21.9g含む
- 鶏むね肉(皮なし)は牛肉よりもタンパク質が多い
- 鶏ささみも牛肉の高タンパク部位より多く含む
- 鉄分や亜鉛は牛肉の方が多く含まれる
- タンパク質は筋肉維持や免疫力向上に重要である
- 適切な摂取量は成人男性65g、成人女性50gである
- タンパク質の過剰摂取は腎臓に負担をかける
- 牛肉は焼く・茹でるなどの調理法で効率的に摂れる
- 肉類だけでなく魚や大豆製品もバランスよく摂るべき
- 牛肉の脂質を抑えたい場合は赤身肉を選ぶとよい
- 牛肉の栄養価を高めるにはビタミンCと組み合わせるとよい










コメント